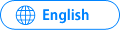- 2026/02/162027・2028年度代議員・役員等選挙についての公示
- 2025/08/182025年度 日本体育・スポーツ・健康学会臨時社員総会開催のお知らせ
- 2025/05/262025年度 日本体育・スポーツ・健康学会定時社員総会開催のお知らせ
- 2026/02/27講道館柔道科学研究会 研究集会(講演会)開催のお知らせ
- 2026/02/27日本ダンス医科学会第16回学術集会開催のお知らせ
- 2026/02/16GEAHSS主催の公開シンポジウムのお知らせ
- 2026/02/07公開シンポジウム開催のお知らせ
ごあいさつ

グローバル化が進む一方で、経済的・軍事的緊張が高まり分断が進む国際社会、新型コロナウィルス感染症のパンデミックの影響、IT化・デジタル化・生成系AIの正負両面の影響など、社会は大きな課題に直面しています。この現状の中で、違いを認め合い、互いを尊重する社会をめざすために、人間が人間らしさを開花させる文化のひとつとして、身体活動やスポーツの果たすべき役割は増しています。
本学会は、定款第3条に記された「体育・スポーツ・健康に関わる諸活動を通じた個人の幸福と公平かつ公正な共生社会の実現に寄与する」ことを目的に、体育・スポーツ・健康科学領域の研究促進と会員の学術的交流を行っています。この目的は、1950年に設立された「日本体育学会」の名称を2021年に「体育・スポーツ・健康学会」へと変更するにあたり、本学会の学術活動と社会とのつながり、社会的意義をより強く意識して策定されました。この目的のもと、16の専門領域と18の地域協力学会が連携しています。また、代議員の女性割合を増やす選挙制度の改革を行った2015年以来、女性理事の割合は恒常的に30〜40%台となり、若手研究者の会も積極的に活動しています。設立から70年を経て、初の女性会長として選出されたことは、本学会が多様性と包摂をめざす国際社会やアカデメイアの一員であることを象徴する出来事のひとつであると受け止めています。
俯瞰的・総合的に議論を行う場である学会大会(年1回)では、現在、全会員が専門領域を超えて5つの応用領域部門(スポーツ文化、学校保健体育、競技スポーツ、生涯スポーツ、健康福祉)に分かれ、社会課題に接近するテーマでのシンポジウムや一般発表に参画しています。異なる専門領域間での議論は、用語の取り扱いが異なるなど、戸惑いもありますが、各自の日頃の研究に創造的な気づきをもたらす機会となっています。
一方で、課題もあります。日本では、第二次世界大戦後、文部省の機構改革に伴い体育局が廃止されました。これにより学校体育、社会体育の行政所掌が分かれるとともに、1964年東京オリンピック以降には、競技スポーツのさらなる普及発展がみられるようになりました。この経緯から、実践への効果的なフィードバックを行うために、各研究の射程が学校体育、生涯スポーツ、競技スポーツという3つの場に限定される傾向がありました。しかし、ジェンダー規範や障害の有無などを乗り越えることによる共生社会の実現、社会の持続可能性等の観点では、3つの場を横断する議論、相互に関連させる議論を深めることが学会には求められます。2023−2024年期の理事会では、こうした課題を念頭に置きながら活動を進め、本学会が学術を通して社会により大きく貢献できるよう努力いたします。
会員のみなさまにおかれましては、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2023年6月17日
学会紹介
一般社団法人の前身である日本体育学会は、1950年2月11日に60人の会員で発足しました。 同年11月、東京大学において第1回の学会大会が開催されました。この時、会員は345名、51題の研究発表がされました。1998年の第49回大会では、13の研究分野において514演題の研究発表・12のシンポジウム・ 11のキーノートレクチャーが行われ、日本体育学会特別企画「体育学の分化と統合」が3年目を迎え、特別シンポジウムが実施されました。第50回記念大会は、 日本体育学会が体育学に関連する他の団体と連合して行う初めての大会として、 1999年10月7ー11日の会期で開催されました。任意学術団体の日本体育学会は、2002年4月に設立総会を開催し、同年6月に社団法人として認可を受けましたが、2008年の公益法人制度改革に伴い、社団法人日本体育学会は、一般社団法人日本体育学会へと移行しました。さらに、2021年4月1日付で、日本体育・スポーツ・健康学会へと学会名称変更し、通称「日本体育学会」とし、新たに歩み出すことになりました。2025年4月時点で、正会員数は5329名、国内の体育学研究領域における最大の学術研究団体です。
日本体育・スポーツ・健康学会の目的は、体育・スポーツに関する科学的研究や関心を高めること、 学際的な交流を促進すること、体育・スポーツ科学を発展させること、 研究で得られた知見を実践の場に応用することです。 さらには、それをもって我が国の学術の発展に寄与することを目的としています。 なお、この目的達成に向けて次の事業を実施しています。
- 学会大会の開催
- 研究発表、講演会等の開催
- 学会誌その他の刊行物の発行
- 調査研究、研究の奨励及び研究業績の表彰
- 会員相互及び内外の関連学会・関連組織との連携協力
- 体育・スポーツ・健康などの政策に関する提言ならびに建議
- 体育学/スポーツ・健康科学の普及啓発活動
- その他目的を達成するために必要な事業